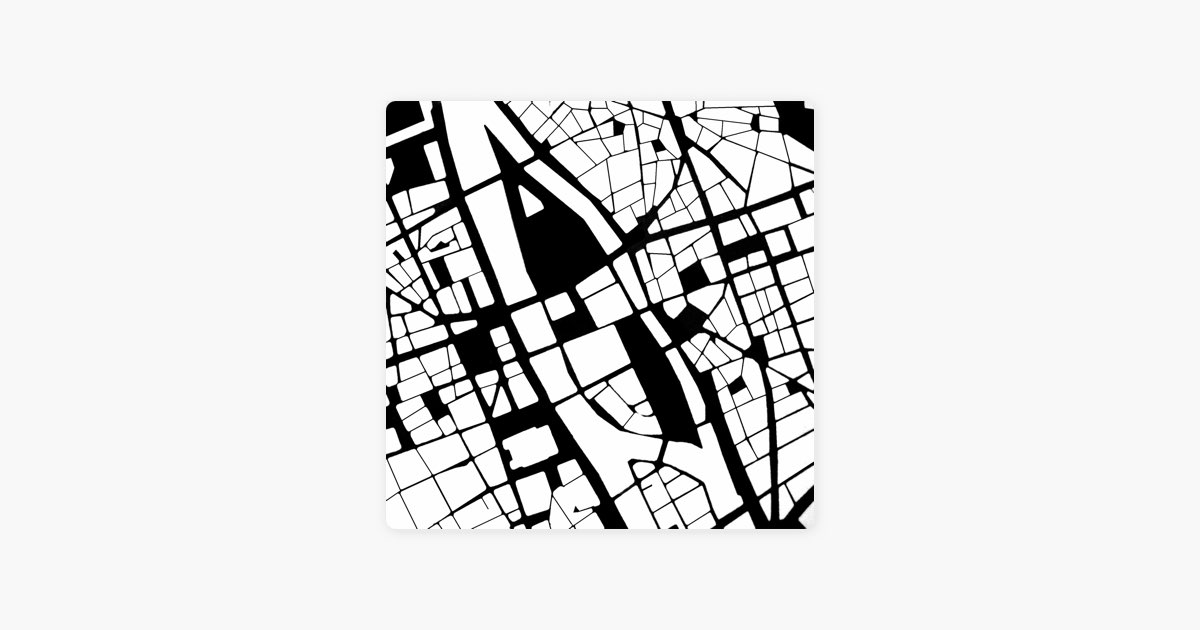Correct Irregulars
WIPPY BONSTACK
アメリカの「WIPPY BONSTACK」による2025年作ですわ!
本作は、非常に実験的というか無軌道極まるサウンドとなっており、下手すれば1フレーズ毎に曲が変化するような展開と変化、そして遊び心が満載なアルバムとなっておりますわ!
ゆるいサウンドが奏でられたかと思ったら、すぐにキレッキレのマスロックサウンドになったりと、聴いている1秒たりとも油断できないのですが、楽曲はしっかりと締まっており、驚異的なバランスで成立している楽曲に驚かされますわ!
曲がそんな状態で成立しているため、聴いているこちら側もかなりの集中力が試される、なかなかハードルの高いアルバムなのですが、この無理矢理楽曲に向き合わされるパワー!これぞプログレの醍醐味の一つとも言えるのではないでしょうか!
若き天才の放つプログレに挑戦ですわ!